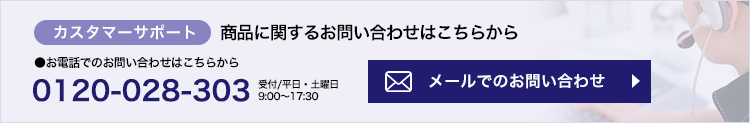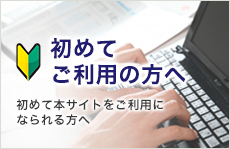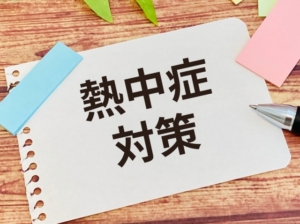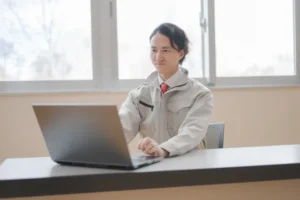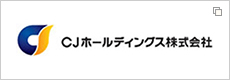点群データとは?導入されている理由と活用シーンを解説
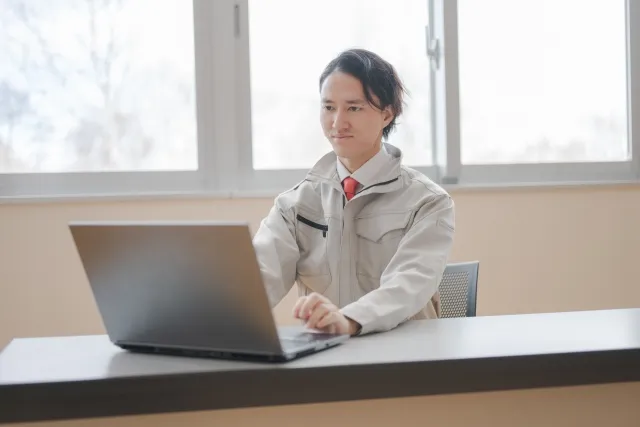
「点群データ」は、建築や土木などの現場で活用されているデータです。ある空間内の点に、座標や色などのデータを付与したものが点群と呼ばれます。
点群データは災害の予防や被災地の罹災状況の把握など、ものづくり以外にも活用の幅が広がっており、エンターテインメント分野や文化財・国宝の保存にも取り入れられています。
この記事では、点群データの特徴や導入されている理由、データの取得方法について紹介します。実際の活用シーンについてもみていきましょう。
そもそも点群データとは
点群データとは、空間や空間内の対象物の形状を高密度の点で3次元に表現された点の集合データです。
1つの点データは3次元座標値(X,Y,Z)と色(R,G,B)からなり、レーザー測量や3Dスキャニングによって取得されます。集まった点群は.txt・.las・.xyzなどのファイル形式で保存されます。
点によって各場所の特徴を示すことで、対象物全体の形やサイズ、細部までを高精度に再現でき、視覚的に状況を把握しやすくなります。
点群データは、次のような分野で活用されています。
- 建設・土木:建物や地形のモデリングなど
- 製造業:製品の品質検査やリバースエンジニアリング
- 医療分野:人体・器官のモデリング
- 地図作成:地形図・都市計画の基礎データ作成
- 文化遺産保存:歴史的建造物や遺跡・文化財のデジタル化
上記は一例で、エンターテインメント分野やその他の学術目的、研究などにも点群データが用いられています。いずれも高い精度で対象物の形状を把握でき、デジタルデータとして保存・共有できます。
点群データの特徴
点群データにはその場所の座標値と色の情報が保存されています。すべての点群について読み込みを行うことで、視覚的かつ立体的な情報が再現できる仕組みです。
空間や対象物がどのような形状をしているのか、どの部分が何色をしているかを再現するために、3Dモデルと呼ばれるモデルを作成しなければなりません。
点群データを取得し、3Dモデルにすることでデジタル化と可視化が行えます。3Dモデルを作成すれば、実体がないところでもさまざまなシミュレーションが可能になります。
点群データが注目されている理由
点群データが注目されている理由として、「3Dモデルを容易に作成できる」「業務の効率化が叶う」「人が作業できない場所での測量ができる」というメリットが挙げられます。それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。
3Dモデルを容易に作成できる
点群データは、点として取得されたデータの集合体であるため、そのままでは活用できません。そこで、3Dモデルと呼ばれるものに変換する必要があります。
3Dモデルとは、データを基にコンピュータ上で作成された立体的なデータモデルのことを指します。
3次元空間内で、オブジェクトと呼ばれる物体を作成し、対象物のモデルとして完成させます。このように作成された3Dモデルは、実物と同様の挙動や外観を再現できます。
点群データは3Dモデルの作成に活用できますが、CADモデルや平面の図面も作成できます。デジタルデータとして中長期的に保存したり、モデルを再現したりすることも可能です。
3Dモデル化の方法①メッシュデータ
3Dモデル化の方法の一つ目は、メッシュデータへの変換です。メッシュデータとは、点群同士を線で結び、三角形などが隣り合ったような形にしたデータのことです。
メッシュデータは、点同士を結ぶ特性から、頂点が角張り、滑らかさに欠けるという欠点があります。頂点の数が多くなるほど滑らかに見えますが、データ量が大きくなり動作が重くなってしまいます。
3Dモデル化の方法②サーフェスデータ
3Dモデル化の方法の二つ目は、サーフェスデータへの変換です。サーフェスデータとは、連続的に変化する値を面的に表す方法です。
点群データをサーフェスデータに変換するためには専用のソフトウェアを使用します。サーフェスに変換することで、土地や地盤、地形などの凹凸が多い環境を視覚的に表現しやすくなります。
業務の効率化が叶う
点群データを活用することで、危険な場所や計測に時間がかかる場所での作業を減らし、必要なデータの取得と活用が可能になります。
一例として、3Dレーザースキャナーやドローンなどを使い、点群データを取得する方法があります。現地で直接計測する必要がないため、短時間でデータを取り込み、3Dモデルとして自動生成できます。
データを自動的に取り込んで活用することで、作業者や関係者間で生じやすい認識の違いや伝達ミスを防ぎ、インフラやその他の業務における管理・保全も効率化されます。
人が作業できない場所での測量ができる
作業員が直接立ち入れない場所や、立ち入りが難しい環境の測量にも、3Dレーザースキャナーやドローンを用いた作業が行われています。
空中から立体的に計測しながら点群データを取得すれば、後からその場所のモデリングを行い、分析や対応を容易に行えます。作業者の人数が限られるような場合や、作業者が1名のみの状況でもスムーズに測量を実施できます。
点群データの取得方法
点群データの取得には、ドローン、3Dレーザースキャナー、移動型レーザースキャナーなどが使用されています。
ドローンを用いたレーザー測量
ドローンを用いた測量とは、ドローンを飛ばしてレーザー光を対象に照射し、データを取得する方法です。
空中から照射されたレーザー光は、対象の地形や建物について点群データとして収集します。上空からの測量であるため移動が容易で、広範囲をカバーできます。
地形や対象物の起伏・凹凸にかかわらずデータを収集できるため、災害の危険性がある場所や人が立ち入れない環境でも測量を実施できます。
3Dレーザースキャナーによる計測
3Dレーザースキャナーによる計測は、対象物の表面にレーザー光を照射し、スキャンして3Dデータを生成する方法です。
レーザースキャナーから発せられた光が対象物に当たり、反射して戻ってくる時間を計測することで、対象物の位置情報が点群データとして取得する仕組みです。
実際の例として、建設現場では3Dレーザースキャナーで建築物を点群データとして取得し、正確な情報の把握や施工管理に活かしています。
移動型のレーザースキャナーによる計測
モービルマッピングシステム(MMS)と呼ばれる移動型レーザースキャナーは、車両に3Dレーザースキャナーまたはカメラなどを搭載し、走行しながら点群データを収集する方法です。
移動型のため車両がデータを自動的に取得する仕組みで、作業者への肉体的な負担を軽減します。労働災害やその他の負担・リスクを低減し、スムーズに測量を進められます。
一例として、配管の内部や災害発生後の道路状態などを適切に把握するために、MMSによる計測が行われています。
関連記事:レーザー墨出し器の使い方は?精度を点検する方法も紹介
点群データが活用される場面
点群データが活用される場面として、インフラ設備や工場設備の整備・メンテナンスや設計検討のほか、災害時の状況確認に利用されています。
インフラ設備の整備や設営検討
点群データは位置関係を正確に把握できることから、インフラ設備の整備や設営検討に役立てられてきました。
ビルやトンネル、橋梁などのインフラ設備の点群データを取得し、3次元でモニタリングすると老朽化・変形・損傷箇所が検出できます。
そこで修復作業や建て替え時期の検討などを行い、さらに長期的な状態変化を記録して保守計画を立案します。
工場設備の設計検討や保守メンテナンス
工場設備の設計や保守・メンテナンスについても、点群データが活用されています。
設備の設計や新規導入については、3Dレーザースキャナーやドローンを使って空間の点群データを取得し、新しい設備機器の配置や変更箇所をシミュレーションし、検討や計画に反映させる流れです。
点群データを使用すれば、工場内や内部の建築構造の3次元モデルを構築できます。設備の摩耗・変形・老朽化の状況もリアルタイムにモニタリングできるため、保守計画やメンテナンス時期の把握が行えます。
災害時の被害状況の確認
地震・洪水・津波・土砂崩れといった災害に見舞われた地域について、地形や構造物の変化を点群データによって可視化するケースです。
ドローンなどで発災後の点群データを記録し、3Dモデルに起こして被害状況を確認します。その後、損傷箇所の特定と必要な修繕作業をリストアップし、復旧計画を立てていきます。継続的にデータを収集することで、地すべりのような進行中のリスクを追跡します。
点群データは土地や建物の状況を可視化する
今回は、点群データの概要や特徴、取得方法と活用事例について紹介しました。
点群データは点の集合体であり、3Dモデルに起こすことで土地や構造物の立体的な情報を可視化できます。メッシュデータやサーフェスデータといった鮮明なデータに置き換えることもできるため、研究開発やリアルタイムでの状況把握に用いられています。
対象物の位置情報や各種測定にも点群データを導入することで、業務の効率化や省人化を実現できます。

 見積りカート
見積りカート
 お問い合わせ
お問い合わせ