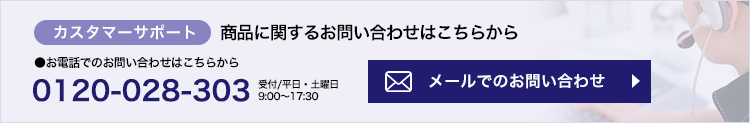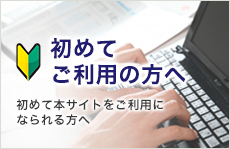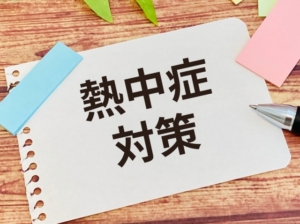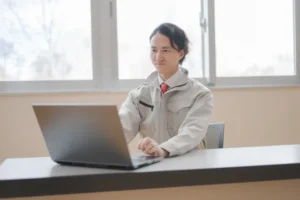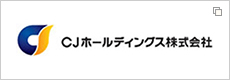絶縁不良とは?絶縁不良を起こす原因・危険性・調査方法を紹介

感電事故や漏電による火災などの原因となる「絶縁不良」は、電気回路に流れる電気が、何らかの原因で絶縁抵抗を低下させた状態です。
すべての電気設備は、不要な箇所に電気が流れていかないように絶縁を行っていますが、経年劣化や故障、その他の原因で絶縁不良となることがあります。
絶縁不良は電気の短絡や感電など、さまざまな事故の原因となる可能性があるため、原因を知って予防することが大切です。
この記事では、絶縁不良の概要や危険性、原因と対処方法を紹介します。絶縁性を測るための絶縁抵抗測定についても取り上げています。
絶縁不良とは
絶縁不良とは、電気を通さない素材でできた絶縁体が正しく機能せず、電気が絶縁体を通り抜けて漏電したり短絡したりする現象です。
本来、絶縁体はゴムやガスなどの絶縁性をもつもので電気を遮断していますが、何らかの原因で破壊などが起きると絶縁不良の状態となり、電気が流れるようになってしまいます。
絶縁不良になると金属が電気を帯び、そこに手や導電性の物体が触れると電気が流れるルートが発生します。絶縁不良を放置していると、漏電から火災や感電といった物的・人的被害を招くおそれもあります。
絶縁不良に伴う危険性
絶縁不良を起こすと、漏電や感電、電波干渉、機器の故障・破損の危険性があります。どのようなリスクがあるのかみていきましょう。
漏電や感電
絶縁不良には、漏電や感電のリスクが伴います。電気が直接漏れ出すため、電気製品や電気設備の金属部が帯電し、そこに触れると強い電流が人体に流れ込みます。感電は重篤なけがや死亡事故につながる危険があり、漏電は火災の危険があります。
電波干渉
電波干渉とは、絶縁不良によって電気回路から高周波信号が伝播し、周辺機器の電波に干渉して動作に影響を与えることです。周辺機器の動作不良や高周波ノイズによる障害にも注意が必要です。
機器の故障・破損
絶縁不良が進むと、電気回路内の電気信号に異常が起きて機械が不具合を起こしやすくなります。電圧制御にも悪影響を及ぼし、配線や部品の故障・破損を招くことがあります。
絶縁不良の原因
絶縁不良は、絶縁体が正しく機能せず電気を通してしまう状態です。一般的には絶縁体が経年劣化などにより機能を失った状態で発生します。
絶縁体が劣化する原因は、紫外線や振動・衝撃、温度や湿度による劣化などがあります。過電圧による劣化も含めて、詳しくみていきましょう。
紫外線による経年劣化
紫外線による劣化は屋外の電気設備に多くみられますが、屋内でも蛍光灯などから影響を受けて劣化が進む場合があります。経年劣化は絶縁不良の主な原因の一つとされています。
太陽光や蛍光灯から出る紫外線は、プラスチックやゴムなどの絶縁材料にダメージを与えます。高分子材料の分子結合を破壊して、強度や柔軟性を低下させます。紫外線にさらされ続けると、絶縁体の表面にひび割れや粉状への崩壊が発生します。
紫外線による影響を避けるためには、耐候性の高い絶縁材料を選ぶ必要があります。また、劣化の程度を定期的に点検して材料を交換することが望ましいです。
振動や衝撃による破損
振動や衝撃も絶縁体に影響を与える現象です。繰り返しの振動、または激しい衝撃によって絶縁体や導体が機械的なダメージを受けると、その部分に破損が起こります。
部品や機器が絶え間なく動き続ける電気設備では、絶縁材料が振動や摩擦によって損耗する場合があります。材料が擦り切れると亀裂などが発生し、わずかなすき間からも電流が漏れる可能性があります。振動や衝撃によって割れや破断につながるケースや、長期間の振動による接触の不安定化や絶縁機能の低下にも注意が求められます。
振動や衝撃による影響を抑えるには、ブッシングやダンパーを必要箇所に設置する、損耗や経年劣化の状況を定期的に把握することが有効です。振動自体を抑える工夫も絶縁体の破損防止に効果的です。揺れの発生源を特定し、機器の配置や接触状況を見直すことが重要です。
温度や湿度による劣化
温度や湿度の変化が、絶縁不良を起こすことがあります。高温の環境では、絶縁材料(特にプラスチックやゴム)が柔化や硬化を起こし、絶縁性能が低下しやすくなります。長期間の加熱で絶縁材料が分解すると、導電性物質を生成することもあります。
低温環境では、絶縁材料が硬化して脆くなる可能性があります。さらに、温度変化が激しい環境では材料が膨張と収縮を繰り返すなどして亀裂が生じ、絶縁性に悪影響を与えることになります。
温度や湿度による変化を防ぐためには、温度や湿度に強い絶縁材料を用いることが有効です。シリコンやエポキシ樹脂のように耐熱性や耐湿性に優れた材料を使用しましょう。
環境への工夫も重要な要素で、防湿対策や設備の設置環境の見直し、空調設備の導入などの対策が有効です。
過電圧による劣化
過電圧とは、許容電圧を超える電圧が回路に加わる状態を指します。電気回路の不具合や落雷によって起こりやすいトラブルで、絶縁体が劣化する主な原因の一つとされています。
絶縁材料には耐えられる電圧(誘電耐力)があり、過電圧が発生しこの電圧値を超えてしまうと、絶縁体の内部で部分的な放電や短絡が発生します。これにより、絶縁材料に局所的な損傷をもたらします。過電圧で導体が異常に発熱し、絶縁材料が変質するケースもあります。
過電圧による劣化を防止するためには、避雷器の設置や適切な回路保護装置を使用します。絶縁材料に過電圧がかかっていないかを定期的に点検したり、部分放電検査やサーモグラフィー検査によって劣化を検出したりする方法も有効です。
関連記事:サーモグラフィーの意味や仕組みとは?3つの特徴と計測時の注意点
絶縁不良の対処方法
絶縁不良の対処方法は、「原因の特定」「事前準備」「修理・交換」「再検査」「予防措置」のステップで行われます。
【原因の特定】
原因の特定として、絶縁抵抗計やサーモグラフィーによる検査を行い、不良箇所を特定します。振動や温湿度などの環境・外部要因も確認しましょう。
【事前準備】
応急処置として、機器・回路に電気が流れないように電源を切ります。不良が発生している箇所を周囲から隔離し、機器や作業者への二次災害を予防します。
【修理・交換】
劣化・損傷のある材料や部品を新しいものへ取り替えます。軽度であれば絶縁テープなどを使って修繕できますが、何度も絶縁体にダメージが加わるようであれば、機器の設計や設置環境などの根本的な要因を見直す必要があります。
【再検査】
修理・交換後に再検査として絶縁抵抗測定を実施します。正しく絶縁され、基準値を満たしているかを確認することが重要です。
【予防措置】
再検査の後も、定期的に検査を実施して点検を行いましょう。温湿度や紫外線、振動などが影響する場所では、一定の期間ごとに定期的な検査や修理が必要になる場合もあります。
環境によっては除湿機やエアコン、紫外線防止カバーや防水対策が必要です。複雑な設備機器や装置の絶縁不良などは、専門業者への修理・点検の依頼が推奨されます。
絶縁不良の発生を検知するためには
絶縁不良の発生を検知するためには、不良箇所を正しく特定するための機器や手法を使用しましょう。
絶縁材料の劣化や異常が起きている箇所のすみやかな特定と、絶縁体の劣化傾向を数値で確認する「絶縁抵抗測定」を実施します。
絶縁抵抗測定に必要な機材
絶縁抵抗測定では、「絶縁抵抗計(メガテスター)」と呼ばれる計器を使用します。スイッチ・ボタンと値を読み取るためのメーターが搭載されています。
絶縁抵抗測定のやり方
絶縁抵抗測定は、はじめに測定対象の設備機器や絶縁抵抗計の準備を行い、本測定に入ります。測定終了後は安全を確認し、データの記録や評価を行いましょう。
| 手順 | 内容 |
| 機器準備 | 測定対象機器の電源をオフにして配線を外し、適切に絶縁する |
| 絶縁抵抗計の準備 | 絶縁抵抗計の設定や動作状況を確認し、適切な電圧範囲に設定する |
| テスト接続 | 絶縁抵抗計のプローブを測定箇所に接続。1つはアースに、もう1つは機器に接触させる |
| 本測定 | 絶縁抵抗計のスイッチを入れて絶縁抵抗値を測定する。表示された測定値を記録する |
| 安全確認 | 測定終了後にプローブを外し、すべての電圧が放電されていることを確認する |
| データ記録と評価 | 測定データの確認と記録を行う。基準値と比較して合否を判断する |
測定時は、電源を切った状態で行いましょう。絶縁抵抗計のプローブ(針)をアースと測定対象の機器に接続していることを確認してください。
絶縁抵抗測定の基準値は、使用する電圧や条件によって異なります。一般的に理想とされる抵抗値は1MΩ以上ですが、省令では以下の基準が定められています。(※)
- 300V以下の使用電圧で、対地電圧が150V以下の場合:0.1MΩ以上
- 300V以下の使用電圧で、対地電圧が150Vを超える場合:0.2MΩ以上
- 300Vを超える使用電圧の場合:0.4MΩ以上
※e-GOV法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)」
絶縁抵抗測定を実施する際の注意点
絶縁抵抗測定を実施する際の注意点として、絶縁保護具を必ず着用してください。事前に機材を確認し、測定の対象となる電気設備は停電状態にしましょう。
①絶縁保護具を必ず着用する
感電の危険に備えるため、摩耗や破損のない絶縁手袋を着用しましょう。規定の保護具を着用し、安全に配慮しながら作業を行ってください。
②事前に機材をチェックする
絶縁抵抗測定では、測定対象の機器や設備に汚れやホコリが付着していないかを確認してください。汚れがあると誤測定につながる可能性があります。設備機器をチェックするときは、電源が入っていない状態で安全に配慮しながら作業を行ってください。
絶縁抵抗計のチェックも忘れずに行いましょう。事前にゼロ確認を行い、「0MΩ」を示していることを確認します。0MΩを示していなければ、別途調整が必要です。
試験は、ガイドラインや説明書などの指示にしたがって正しく行いましょう。対象の電気機器や設備に過度な負荷を避け、長時間や高電圧による試験は控えることが望まれます。
機材以外では、測定環境にも配慮する必要があります。高温や低温、多湿または振動の多い環境では測定誤差が発生する可能性があるため、測定に適した環境を選びましょう。
③測定対象を必ず停電状態にする
感電の危険性や機器内部へのダメージのおそれがあるため、測定対象は必ず停電状態にする必要があります。
ブレーカーを遮断し、検電器で停電状態になっていることを確認します。絶縁抵抗計が0MΩと表示されていることを確認してから測定に入りましょう。
絶縁不良の危険や原因をチェック
今回は、絶縁不良の概要と危険性、発生原因や対処方法について紹介しました。
電気を通さない絶縁体は、経年劣化や衝撃などにより絶縁性能が低下するおそれがあるため、定期的な点検や修理・交換が必要です。
電気機器や電気設備は、絶縁状態が適正かどうか、定期的に測定を実施することが求められます。絶縁抵抗測定では正しい値を示す絶縁抵抗計を使用し、流れに沿って正しく計測を行ってください。
計測前の準備や結果の記録など、各プロセスを適切に実施することが重要です。正しい方法を意識することで、電気機器や電気設備を安全に運用することができます。

 見積りカート
見積りカート
 お問い合わせ
お問い合わせ