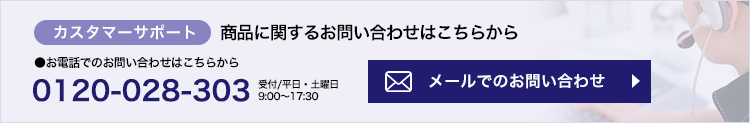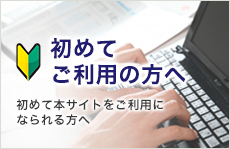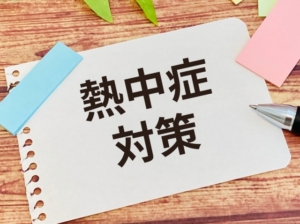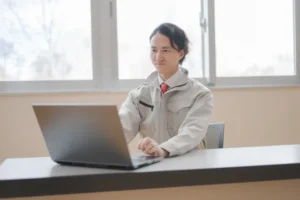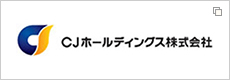計測器の特徴・目的と具体的な使い方・計測器が活躍する産業

計測器・測定器は測量や製造の現場に加え、研究開発、環境調査、フィールドワークなどの分野でも活用されています。
対象物の状態を正確に把握し、正しい数値に基づいて建物を建てたり製品を作ったりするためにも、計測機器の存在は不可欠です。
ここでは、計測器と呼ばれる機器の特徴や「計測」と「測定」の意味の違い、計測器として用いられている具体的な製品を紹介します。
計測器が活用される代表的な産業「自動車」「半導体」「航空機」業界についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
計測器とは
計測器とは、温度・長さ・重さ・密度などのサイズや質量に加え、加速度、圧力、放射線のような目に見えない物理量を可視化する機器です。
計測器という名称は測定器・測定機・ 計器・標準器といった機器の総称で、それぞれの機器が異なる用途に使われています。
高い精度で数値を計測できるものの、経年劣化や繰り返しの使用によって結果に差が生じる可能性があるため、定期的に「校正」という作業を行い、正確さを保ちます。
”計測”と”測定”は何が違う?
計測は「機器を使って数・量・重さ・値などをはかること」という意味があります。広義には、物理量や物質の状態をはかる行動のことです。
ここでいう機器とは、温度計のような比較的小さなものだけではなく大型の装置も含まれます。数や量をはかるためにさまざまな機器が使われるという意味であり、計測という言葉にはデータを得るためのプロセスが強調されています。
測定は「器具や装置で重さ・早さなどをはかること」ですが、「直接測定するだけではなく、理論的に間接的に行う方法」も含まれています。
値をはかる行為という意味においては、計測と測定は共通していますが、「握力測定」「血糖値測定」「通信速度測定」といった例のように、測定という言葉が使われるシーンは具体的で特定の状況や対象を指し示すことが多く、計測よりも具体的な場面で用いられる言葉です。
「値をはかる」という意味では共通していますが、計測はさまざまな機器・装置を用いて値を求めるという広い意味で用いられるのに対し、測定は対象を定量的に評価し、具体的な値を出すという意味で使われているという違いがあります。
計測を行う目的
計測を行う目的は次のとおりです。
【データ収集】
特定の状態や現象の情報を集めるために計測が行われます。研究・開発や安全の確保といったさまざまな目的の前段階としてデータを集めます
【研究開発】
新技術や新製品の研究・開発を目的として計測が行われます。正確性の高いデータが得られるほど理論の実証や新しい知見の獲得に役立てられます。
【品質管理】
品質管理は、製品やサービスの品質を確保するためのさまざまな手法を指します。製品の寸法を計測し基準値を満たしているかを確認することで、製品ごとの誤差やばらつきをなくす方法もそのひとつです。
【安全の確保】
建物や構造物が経年劣化しているとき、危険な状況の発生を防止し、危険性を予測・判断するために計測が行われます。対象物にX線などを照射し、内部の構造を取得する構造計測がその一例です。
【診断や治療】
医療分野では、患者の血液や血圧などのデータから状態を把握するために計測が行われています。画像診断と計測、問診と計測といった複数の手法を組み合わせて、治療の方向性を決定します。
計測器の具体例
計測器には、三次元測定機や画像測定機、マイクロメータなどさまざまな種類が用いられています。
| 種類 | 用途 |
| 三次元測定機 | 対象物の位置・形を三次元的に測定する |
| 精密センサ | 位置決めや物体検知などを行う |
| 画像測定機 | 画像処理技術によって対象物を測定する |
| 測定顕微鏡 | 対象物の寸法の測定や観察を行う |
| マイクロメータ | 対象物の厚み・長さなどを測定する |
温度計や湿度計のような身近な製品も計測器の一種ですが、ここでは5つの専門的な計測器についてみていきましょう。
三次元測定機
三次元測定機は、物体の形や寸法を三次元的に正確に測定する装置です。
製造業や工業の分野で活用されることが多く、きわめて高精度な測定が可能なことから、座標や寸法の測定や部品の適合性確認などに使われています。
種類として、中小サイズの測定に使われるブリッジ型や大型の構造物を対象としたアーム型などがあり、対象物や用途に応じて選定されます。
精密センサ
精密センサは、高精度に物理的・化学的・生物的な情報を検出し電気信号などに変換する装置(部品)です。
工業や医療、環境や科学技術といった幅広い領域で使用され、高感度かつ安定性に優れたものが精密センサとして用いられます。
一例として、温度の計測に使われるものは温度センサ、光の強度・波長を検出するものは光学センサと呼ばれ、用途に応じてさまざまな種類が存在します。
関連記事:眩しさの単位・輝度とは?照度や光度との違いや基準を紹介
画像測定機
画像測定機は、光学的手法によって物体の形状、寸法、特性を計測する装置です。
一例として、製品の品質検査や寸法の正確な測定などに利用され、設計図面通りに製品が作られているかを確認します。
高精度の画像測定機は、デジタルイメージング技術を搭載し通常の画像測定機よりもさらに微細な形状や寸法を捉えることが可能です。また、高速での計測や3Dプロファイリングに対応した製品もあります。
測定顕微鏡
測定顕微鏡は、顕微鏡を搭載し微小な対象物の形状や寸法をはかる装置です。
拡大観察機能に寸法計測機能を組み合わせた計測器で、目視や通常の拡大では見えない細部の観察や微小な製品の評価に使用されています。
数十〜数百倍の拡大率をもつものは、肉眼で見えない微細な構造や寸法を観察します。角度や曲率なども求められるため、対象物がどのような形状をしているか正確に捉えることが可能です。
マイクロメータ
マイクロメータは、測定する対象物を挟み込んで外径・長さ・厚みなどを測定する工具です。
機械分野で多く用いられる計測器で、精密なネジを使って高精度に計測が行えるという特徴があります。製品の種類によっては1μm単位までの測定が可能なものもあります。
外測・内測・棒型・3点式内測などいくつかの種類があり、計測の目的に応じて使い分けられています。
計測器が活躍する産業
計測器は幅広い産業で活用されており、製造業・工業では正確な計測を行うために欠かせない機器です。
ものづくりの現場では、製造の前段階で部品の状況を正しく把握し、想定どおりに加工が行えるかを判断しなければなりません。また、製造後は製品の状態をひとつずつチェックし、仕様どおりの設計や許容された値に収まっているかを検査しなければなりません。
目視で検査できない部分まで効率的に精密な測定を行うために、計測器は重要な役割を担っています。
ここからは、特に計測器が活躍する自動車産業・半導体産業・航空機産業についてみていきましょう。
自動車産業
自動車産業では、自動車関連製品の安全性や性能を確保し、安定的な生産効率を維持するために計測器が活躍しています。
車両や部品が仕様通りに造られているかを確認するために、計測器を用いた寸法検査や摩耗検査が行われています。生産ラインでは不良品の発生を抑えるためにリアルタイム計測を実施し、高速かつ高い精度で測定を実施します。
近年では環境規制への対応として、燃費や排出ガスにかかわる計測も行われています。また、次世代の新しい技術や素材を評価するためにも計測が実施されており、電気自動車用バッテリーの性能試験がその一例です。
半導体産業
半導体産業は、電子機器や装置の中核を担う半導体を製造する産業です。微小なスケールでの製品設計・製造が求められるため、高精度の計測器が活用されています。
プロセス制御として、半導体の製造プロセスにおけるフォトリソグラフィや成膜などのリアルタイム監視、ウェハやチップの欠陥を検出する品質管理、ナノスケールで仕様の適合性を評価するなど、各工程で計測器が導入されています。
他にも、半導体材料の特性評価や加工後の寸法測定、製造現場における環境管理にも計測器が欠かせません。
航空機産業
航空機産業では、高い安全性が求められる航空機の部品・構造を維持するため、計測器による定期的な評価や検査が実施されています。
三次元測定機を使った正確性の高い検査や設計通りの性能が発揮できることを確認する性能評価、構造強度を確認するプロセスや飛行中の振動を評価する際にも計測器が活用されてきました。
航空機産業では、設計・製造から運用・保守に至るまで一連の工程を計測器が支えています。
計測器は幅広い産業で活躍する測定機
今回は、計測器の概要や目的、どのような産業で使われているかなどを紹介しました。
計測器は、重さ・長さ・密度などの値を求めるために使われる機器です。精密さが求められる航空機・半導体産業のほか、ものづくりの分野である自動車産業や工業・研究・環境分野など幅広い領域で用いられています。
製品によって差や狂いが発生しないように予防し、不良品を除くうえでも重要な役割を果たしており、安全性や耐久性の確保、製品や構造物の長寿命化などにも役立てられています。

 見積りカート
見積りカート
 お問い合わせ
お問い合わせ