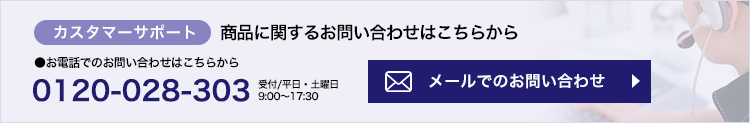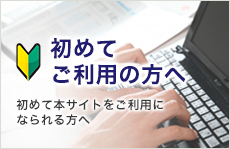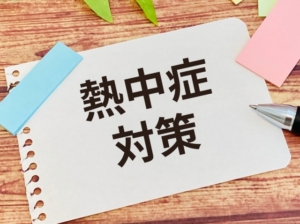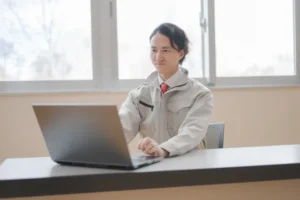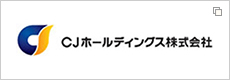事業者への熱中症対策の義務化と現場で実施すべき予防策を解説
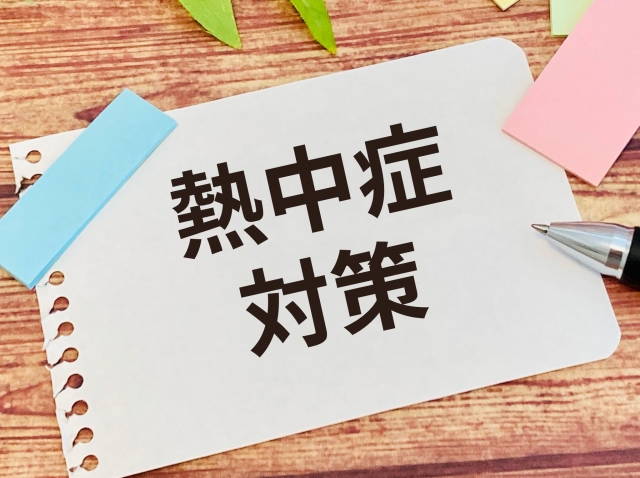
夏季を中心に気温の高い日が増加し、それに伴って熱中症のリスクが深刻になっています。
屋外作業や高温環境での作業には熱中症のリスクが伴うため、作業者本人だけでなく、事業者も適切な対策を講じる必要があります。
事業者は作業者に安全な環境を提供する必要があり、政府は2025年6月1日より、熱中症防止のための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」を事業者に義務付けました。
この記事では、熱中症対策の義務化の目的と背景、義務付けられた対策や効果的な対処方法について解説します。
熱中症対策義務化の目的と背景
熱中症対策が義務化された背景には、地球温暖化による気温の上昇や猛暑日の増加によって発生する死亡災害の問題があります。
職場では作業者の安全を守るための安全管理が求められていますが、法令の不備により対応が十分に行われておらず、作業者への肉体的な負担が見逃されてきた経緯がありました。
猛暑の増加と安全管理の緊急性
熱中症対策が義務化された理由のひとつが、地球温暖化の影響による猛暑日の増加です。
日本では都市部のヒートアイランド現象も影響し、夏季に限らず気温が異常に高くなる日が増えています。
気候変動は日常生活に加え、屋内外の労働環境にも深刻な影響を及ぼしています。日中の屋外作業をはじめ、空調が不十分な屋内作業でも熱中症にかかる危険が生じます。
熱中症のリスクが年々高まるなか、事業者は従来の自主的な取り組みに加えて、法的義務として対策を講じることが求められます。
熱中症の職場死亡災害事情
厚生労働省の報告によれば、熱中症による労働災害は年々増加傾向にあり、特に夏場の建設現場や運送業、製造業などでは多くの死傷事故が発生しています。(※)
厚生労働省が発表した2023年(令和5年)の職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)の数は1,106人(前年比279人・34%増)で、建設業と製造業が全体の約4割を占めました。
熱中症による死亡者の数は31人(前年比1人・3.3%増)で、建設業と警備業でそれぞれ5人以上の死亡者が発生しています。
※参照元:厚生労働省「令和5年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します」
現行法令の不備
従来の労働安全衛生法や関連通知は、熱中症対策について一定の指針を示してはいたものの、事業者に対する具体的な義務規定が不十分でした。
一例として「労働者に対し水分補給の機会を設けることが望ましい」といった内容が中心で努力義務にとどまり、法的拘束力に乏しい状況も熱中症による事故を防げない一因となっていました。
努力義務のみでは事業者間の対応がばらつき、十分な対策を講じないまま放置されてきたケースも少なくありませんでした。
こうした背景を受け、事業者に熱中症対策を義務付けるための労働安全衛生規則が改正されたのです。
対象となる作業環境・条件
次に、熱中症対策義務化の対象となる作業環境・条件についてみていきましょう。
- 作業環境:WBGT28度以上/気温31度以上の環境
- 作業時間:連続1時間以上/1日4時間以上の実施が見込まれる作業
WBGT値(WetBulb Globe Temperature:湿球黒球温度)は暑さ指数のことで、気温・湿度・輻射熱・風速といった要素を考慮して、熱中症のリスクを評価する指標です。
WBGT指数計を設置することで、作業環境ごとのWBGT値を把握することができます。WBGT値が28度以上または気温が31度以上の場所で継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超える作業が行われる場合は、必ず熱中症対策を実施しなければなりません。
作業環境の条件はどれぐらい当てはまる?
環境省では、熱中症予防情報サイトとして全国の暑さ指数を公開しています。(※)
東京と大阪で昨年の6〜8月のうち、昼間の最高暑さ指数が28度を超えた日数は次のとおりです。
| 地点/月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 東京 | 8日 | 25日 | 29日 | 14日 |
| 大阪 | 3日 | 25日 | 29日 | 9日 |
東京と大阪はどちらも7月と8月に暑さ指数28度以上の日が25日を超えていました。
9月に入っても暑さ指数30度を超える日もあり、長い期間で熱中症対策が必須であることがわかります。
※参照元:環境省「熱中症予防情報サイト」
条件に当てはまりやすい業種
屋外での作業や高温多湿な環境下での作業が多い業種は、熱中症のリスクが高くなります。
条件にあてはまりやすい業種は以下の通りです。
- 建設業
- 製造業
- 農業
- 運輸業
- 警備業
- 商業
- 清掃・と畜業
- 林業
上記では建設業における死傷者がもっとも多く、ついで製造業の割合が多くなっています。
企業に義務付けられる対策
企業に義務付けられる対策として、報告体制の整備・手順作成・関係者への周知が挙げられます。
流れに沿ってそれぞれの対策を詳しくみていきましょう。
報告体制の整備~見つける~
熱中症の疑いがある症状に気づいた際、速やかに報告できる体制の整備が必要です。作業現場での異変を早期に「見つける」ことが対策の第一歩となるため、誰が・どのように・どこへ報告するのかを明確にし、現場全体で共有しましょう。
手順作成~判断する~
報告を受けた後は、状況を正しく「判断する」ための基準や手順を整えておくことが重要です。熱中症の初期症状を見逃さず、迅速に対応判断ができるように、緊急連絡先や医療機関の情報、搬送の手順などを具体的に定めましょう。
現場の状況にかかわらず一貫した判断ができる体制が求められます。
関係者への周知~対処する~
適切な「対処」を行うためには、全関係者への周知が不可欠です。熱中症は個人の体調や持病により影響が異なるため、全作業者が自分ごととして理解し、行動できるようにする必要があります。朝礼やミーティング、社内メール、掲示板などを活用し、報告体制や対応手順を繰り返し周知しましょう。
違反した場合の罰則とリスク
2025年6月1日に熱中症対策が義務化されたことで、法的な罰則だけでなく、企業としての信頼を損なうリスクも生じます。ここでは、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
罰則
事業者が適切な熱中症対策を講じていない場合、労働安全衛生法第119条に基づき、6か月以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金が科される可能性があります。万が一、労働者が熱中症で重大な健康被害を受けた場合には、さらに重い処分が下されることもあります。
リスク
熱中症対策を実施しなかった場合、法的な罰則だけでなく、次のような企業リスクにも注意が必要です。
- 社会的信用の低下:安全管理が不十分な企業として、取引先や求職者からの信頼を失う可能性
- 労働基準監督署からの指導・監査:一度違反が発覚すると、継続的な監督や是正指導の対象となる
- 従業員の離職や士気低下:安全対策が不十分な職場環境は、従業員の不安や不満を招き、離職の要因になり得る
熱中症対策の義務化は、単なるルールではなく、「働く人の命と健康を守る責任」です。罰則やリスクを正しく理解し、実効性のある対策を進めることが、企業経営の安定にもつながります。
企業の準備と対応フロー
次に、企業が熱中症対策を行う際の準備と対応フローをチェックしましょう。
対象業務の洗い出し
企業は、自社の業務で熱中症リスクが高い作業や環境を明確にします。
気温や湿度が高いために身体に負担がかかる業務を抽出し、現場の特性に応じてリスク評価を実施したうえで、優先的に取り組む対策とその順位を定めます。
熱中症の早期発見に向けた体制の整備
現場で異常を訴える作業者や周囲の作業者の声を拾えるように、体制の整備や熱中症の初期症状に気づくための教育訓練を実施します。
現場におけるWBGT値(暑さ指数)の常時測定と、異常発生時のフローをマニュアル化するといった対策も重要です。
マニュアル・実施手順の作成
熱中症の疑いがある労働者を発見・把握したときは、迅速かつ的確な判断が求められます。重篤化を防ぐために、必要な措置を迅速に講じることが重要です。
実施手順については、「作業からの離脱」「身体の冷却」「医療機関への搬送・診察」などをフローとして整備します。事業所ごとに連絡網や搬送先の連絡先・所在地をピックアップし、関係者に周知したうえで手順を定めておきましょう。
制服を着用している場合は衣類を緩める、意識がある作業者には水分・塩分を摂取させるといった細かな対応も重要です。ただし無理に対応することは避け、体調や状況に応じた手順をあらかじめ定めておく必要があります。
熱中症疑いのある作業者が問題ないと申し出ても、異変がある場合はすみやかに救急隊を要請するか、医療機関へ搬送します。判断に迷った場合は「#7119」サービスを活用するなど、予防や早期発見につながる体制を構築することが重要です。
手順を定めたあとは、関係者全員へ周知し、一度限りではなく、継続的に周知を行いましょう。熱中症患者の状態は熱失神や熱射病など、症状の重さによって現れ方が異なるため、臨機応変に措置を講じられるように準備しておきましょう。
周知を目的とした教育や研修
熱中症患者を早期に発見・把握し、適切に報告や医療機関へ連携をとるための実施手順は、作業にかかわる関係者全員に漏れなく周知しなければなりません。
さらに、周知だけではなく内容を深く理解してもらうことが重要です。文書を配布するだけでなく、予防策や重篤化時の危険性についてもあわせて周知しましょう。
熱中症予防のための周知については、厚生労働省や環境省が運営するサイトに掲載されている教材やリーフレットの活用が推奨されています。一例として、厚生労働省のリーフレットを参照元として提示することで、視覚的にわかりやすく情報を提供できます。(※)
事業者で自ら教育が行えない場合は、外部の団体が実施する教育イベントを活用する方法もあります。
必要な備品・設備の整備
熱中症対策を策定し、現場で機能させるためには、必要な備品や設備の整備も不可欠です。
暑さ指数を計測するための計器の設置と点検・メンテナンス、作業者一人ひとりのバイタルチェックをリアルタイムに行うためのデバイスやツールなどを導入しましょう。
また、水分・塩分がすぐに補給できるように環境を整備したり、作業時間の短縮や気温の高い時間帯を避けたりといった工夫も重要です。
備品や設備を整備したあとは、使用方法を明記したマニュアルを作成しましょう。日本人以外の外国人作業者にも理解できるように、日本語以外の言語で表記したマニュアルがあると安心です。
実施と点検
熱中症対策を実施したあとは、結果を記録・分析して見直しや改善に繋げましょう。声掛けや対策が形骸化すると、異常発生時の対応が遅れ、重篤化につながるおそれがあります。
PDCAサイクルを回しながら、現場の状況や実情に見合うように、現場の実情に合った熱中症対策を整備し、継続的に見直していきましょう。
効果的な熱中症対策方法
熱中症は作業者のバイタル情報を分析することで、効果的に予防することができます。ここからは、現場でおすすめの熱中症対策ツールをみていきましょう。
現場におすすめの熱中症対策
屋内外での作業を見守る「みまもりがじゅ丸®」は、企業向けインターネットソリューションを提供する株式会社NTTPCコミュニケーションズのIoTサービスです。
専用のデバイス(活動量計・中継機器)から取得した脈拍情報と位置情報を活用し、現場作業者の体調をリアルタイムに確認します。万が一急激な変化がみられた場合には、作業者に速やかに対応し、早期に熱中症対策を実施できます。
作業者は目の前の業務に集中しているため、自発的にバイタルチェックを行うのは困難です。しかし、デバイスを活用することで個々の状態を把握できます。
本サービスは、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)において、安全・健康管理システムの評価済みサービスとして登録されています(※)。
※NETIS登録番号:HK-190006-VE
熱中症対策の義務化に合わせた対策が求められる
今回は、企業が取り組むべき熱中症対策のポイントと、重要性や実際の流れについて解説しました。
熱中症は夏季に限らず、年間を通じて予防が求められる健康被害です。事業者全体で取り組むべき課題であり、作業者への教育と意識の向上が不可欠です。
重篤化や死亡事故を防ぐためにも、周知を徹底し、定期的な研修や情報提供に取り組みましょう。
現場では作業者の体調をリアルタイムに確認できるツールを活用し、熱中症を予防し、安全で効率的な職場環境を目指しましょう。

 見積りカート
見積りカート
 お問い合わせ
お問い合わせ