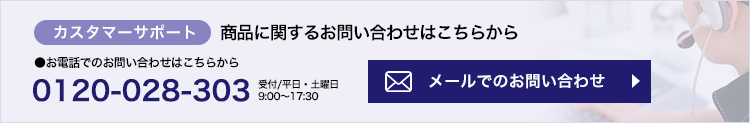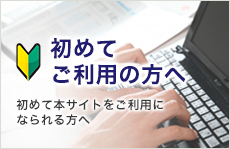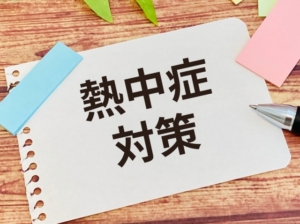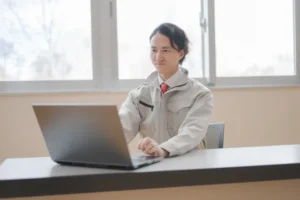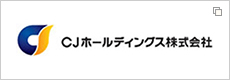コンクリートの養生とは?養生の方法・種類と失敗事例を解説

コンクリートを用いた作業では、「養生」と呼ばれるプロセスが不可欠です。
養生とは、コンクリートの強度・耐久性・水密性を高めるために必要な工程です。
生コンクリートを枠内に流し込む行為は「打設」と呼ばれ、打設が完了すると養生のプロセスに入ります。養生は、堅牢な基礎を構築するために欠かせない工程でもあります。
この記事では、コンクリートの養生についての基本的な知識と養生方法について取り上げています。養生の失敗事例や、成功させるためのポイントについてもみていきましょう。
コンクリートの”養生”とは?
コンクリートを使った構造物や建造物を造るうえで必要となる「養生」は、次の行為を指す言葉です。
- セメントの水和反応を進めるために水分を与える
- 材料から水分がなくならないように防ぐ
- 水和反応が適切に継続するように温度を制御する
- コンクリートが硬化するまで保護する
コンクリートは、打設を行ってすぐにきれいに固まるわけではなく、一定レベル以上の温度と水分を含んでいなければなりません。
そこで、上記のようなプロセスが必要となり、打設部分を保護しながら硬化させていきます。
コンクリートの養生方法
コンクリートの養生には加熱や湿潤など目的が異なり、状況に応じた方法を選ぶ必要があります。
ここからは、養生方法と目的について詳しくみていきましょう。
湿潤養生
湿潤養生とは、コンクリートを硬化させる際に水分を保ちながら乾燥を防ぐ方法です。
湿潤養生には、複数の手法が存在します。「散水養生」はコンクリートの表面に水を一定間隔で撒きます。「湿布養生」は保水シートやマットでコンクリートの上を覆い、水分の蒸発を防ぎます。「湛水養生」はコンクリート表面に水を張る方法です。
他にも噴霧や湛水など、さまざまな方法で水分を保持することが可能です。コンクリートの表面が乾燥しすぎてひび割れが発生したり、コンクリート内部の水分が失われるのを抑えたりできます。
湿潤養生での期間の目安
湿潤養生は、コンクリートの強度や耐久性を確保するうえで重要な工程です。コンクリートが直射日光や風にさらされた場合の乾燥を防ぐためにも重要な作業工程です。
湿潤養生の期間は、コンクリートの用途や施工環境によって変動します。一般的には、7日間ほどかけて湿潤作業を行います。通常よりも早く硬化する早強コンクリートはそれより短期間で済む場合もあります。
低温の環境下では水とセメントの水和反応が遅れるため、10日以上かけることが推奨されます。
保水養生
保水養生は、コンクリートに必要な水分を確保し、水和反応を適切に進行させるための方法です。
湿潤養生と混同されやすい方法ですが、コンクリート内部の水分を保つことに重点を置いています。水分を追加するのではなく、コンクリートを覆って蒸発を防ぐ方法です。
具体的には、コンクリート表面を特殊な保水シートやマットで覆います。また、コンクリート膜養生材の塗布を行い、水分を保持する場合もあります。湿潤環境を維持しながら水分が蒸発しないように抑える方法もあります。
保水養生は気温や湿度が低い環境下で重要な作業です。十分に保水処置を行わなければコンクリートの表面が乾燥し、ひび割れのリスクがあるためです。
保温断熱養生
保温断熱養生は、コンクリートの硬化過程で適切な温度を維持することで、凍結や乾燥を防ぐ方法です。
寒冷地や冬季にコンクリートを施工する際に重要な工程で、凍害の防止やコンクリート内部の水和反応の促進、強度や耐久性の確保を目的としています。
保温断熱養生では、発泡ポリエチレンやアルミ蒸着シートのような断熱材でコンクリートを覆う方法や、ヒーター・温風機を使ってコンクリート周囲の温度を保つ「加熱養生」などが行われています。断熱性能に優れた型枠を使用し、温度を保持する「型枠断熱」という方法も採用されています。
コンクリートが凍結すると、内部の水分が膨張してひび割れを引き起こす要因となります。そのようなリスクを軽減し、適切な強度を得るためにも保温断熱養生は不可欠のプロセスです。
給熱(加熱)養生
給熱養生(加熱養生)は、コンクリートの凍結や凍害を防ぐために、コンクリート自身または周囲に熱を与える養生です。
外気が低い寒冷地や冬季の施工において必要となるプロセスで、寒さがコンクリートの硬化に影響を与えるおそれがある場合に行われます。
「蒸気養生」はコンクリートの表面や型枠内に蒸気を与えて、温度と湿度を一定に管理する方法です。「電熱養生」は電熱マットや電熱線を使い、直接対象に熱を加えます。「温風養生」は専用の温風機を使ってコンクリート表面や周囲の空間を温める方法です。
工場や屋外などそれぞれの環境に適した手段が採用されています。効率的に加熱を行うために、温度を保持できる加熱型枠が使われることもあります。
冷却養生
冷却養生は、コンクリート材の一部またはすべてを事前に冷却して打ち込み温度を下げた状態で施工する方法です。
高温の環境下で打設される際に行われる養生法で、コンクリートの品質を保持し急激な乾燥やひび割れのリスクを抑えます。
冷却養生には、冷却水をコンクリート表面にかけたり冷却シートを巻き付けたりする方法があります。また、コンクリートの配合時に氷を混ぜ込むものや、コンクリート内部に冷却管を設置して直接温度管理を行う方法もとられています。
冷却養生は暑さが厳しい夏季や、直射日光の照りつける場所、大規模コンクリート構造物の施工時などに有効とされており、適切な温度に維持することでコンクリートの強度や耐久性を向上させることができます。
促進養生
促進養生とは、コンクリートの硬化を加速するために温度・湿度などの条件を制御する方法です。
促進養生を適切に実施することで、短期間のうちに必要な強度を確保したり工期を短縮したりできるほか、施工の効率化が図れます。
「蒸気養生」は、蒸気を使って温度や湿度を上げ、硬化反応を加速させます。「加熱養生」はお湯や電気を使ってコンクリートを加熱する方法です。他にも保温シート・断熱材・化学物質の混合といった方法がとられることもあります。
促進養生は過度に行うと内部組織の劣化を招くおそれがあるため、慎重に条件を設定し管理しなければなりません。設計・施工の仕様やガイドラインの遵守が求められます。
コンクリートの養生に失敗してしまった場合
コンクリートの養生に失敗してしまった場合に考えられる問題として、ひび割れや凍害、耐久性の低下が挙げられます。それぞれの失敗についてみていきましょう。
ひび割れが発生する
養生が不十分な場合、乾燥収縮や温度によるひび割れが生じやすくなります。内部の水分が凍結・融解する場合もひび割れの原因となります。
凍害が生じる
コンクリートの凍害とは、内部に含まれる水分が凍結し、強度が得られない現象です。
-0.5〜2.0度の凍結温度において、水分が凍結し体積が膨張すると水圧が発生し、コンクリートを破壊します。
耐久性が低下する
養生が十分に行われていないと、乾燥収縮や強度不足による耐久性の低下が起こりやすくなります。
具体的には、コンクリートが乾燥して水分が不足する、塩害や中性化などによる科学的要因による耐久性の低下です。
コンクリートの養生を成功させるためには
コンクリートの施工に欠かせない養生のプロセスを成功させるためには、施工ガイドラインを遵守し作業環境に適した方法を選びましょう。
正しい作業手順を守り、専用の計器(計測器)を活用して、温度管理や湿潤状態の管理を行っていくことが大切です。
関連記事:計測器の特徴・目的と具体的な使い方・計測器が活躍する産業
コンクリートの養生を成功させるためには計器を活用
今回は、コンクリート打設後の養生について、基礎知識や養生の方法を紹介しました。
コンクリートを使った施工では、適切な温度・湿度と水分が求められます。施工時の状態にもよりますが、コンクリートがどの程度乾燥しているかは目視だけでは把握できないため、専用の計器と定期的な養生が欠かせません。
養生には保温断熱養生や保水養生など、それぞれの環境や目的に適した方法があります。計器を使って状態を把握し、コンクリートの劣化やトラブルを防ぎましょう。

 見積りカート
見積りカート
 お問い合わせ
お問い合わせ